練習できない日、私はすごくつらいんです。特に持病があると思うように楽器が弾けない日があります。リウマチになったばかりの頃はその楽器を弾けない日がとてもつらい時間でした。
でも今では「練習できない日」ではなくて、「音楽している日」と考えを変える日にしています。
今日は私が実践している“楽譜と向き合う時間の過ごし方”の一部分をお伝えします。
病気の時だけではなく、気分が乗らない日、集中できない日にも使える方法です。
なぜ「弾けない日」に楽譜を読むのか
楽器を実際に弾くことだけが練習ではありません。
楽譜を深く読むことで、音楽の構造、作曲家の意図、表現のヒントが得られます。実演する前に頭の中で丁寧に準備しておくことは、身体で弾けるようになった時の上達速度をグッと引き上げます。特に体力や調子に波がある人にとって体を休めながらできる「音楽の勉強」は強力な武器になります。
具体的な「楽譜ワーク」4つ
以下は私が実際にやっているメニューの一部です。
①楽語・記号チェック
楽譜の指示を丁寧に読む
- 書かれている楽語を確認
- 強弱記号、アクセント、テンポ変化をマーク
→まだ読み込めない学習者さんは「どんな指示があるか」をチェックするだけでも世界が変わります。
②楽譜を見ながら音源を聴く
- SpotifyやCD、YouTubeで複数の演奏を聴き比べる。
- 聴きながら楽譜に気づきメモ(表現の引き出しが増え、自分の音楽作りに直結します。)
③スコアを読む
- 伴奏譜やスコア(総譜)をざっと眺める。
- 自分のパートがどう他の西武と絡むかを確認(アンサンブル感が育ちます)
④作曲家・曲の背景を調べる
- 作品の作曲された背景、作曲家の人生史、などを調べる。
- 小さなトリビアを書き留める(曲への理解が深まり、表現に厚みが出ます)
実践のコツ(病気や気分が乗らない日の工夫)
- 短時間で区切る:無理に長時間やらず、5〜10分の区切りで進める。
- 目に見えるメモを残す:楽譜に付箋で書き込みをするなど
- やることリスト、やったことリストを作る:項目チェックで達成感Up↑
楽譜ワークがもたらす具体的なメリット
- 音程の安定:出したい音の想像が働くのでその音を出そうとする。
- 表現の選択肢が増える:楽譜に書いてあることや、参考音源を元に頭の中で「どうしたいか」が明確になっているので表現がしやすい状態になる。
- 本番やレッスンでの仕上がりが早くなる:弾けるようになるスピードが上がるので、当然仕上がりも早くなる。
- 気力が回復した時の練習効率が上がる。
まとめ
練習できない日は、決して後退ではありません。楽譜に向き合うことで、別の角度から「音楽をしている」時間を作ることがでkます。
今日の小さな積み重ねが、明日の一音を大きく変えます。焦らず、自分のペースで音楽を育てていきましょう。
(プロを目指すみなさんは、弾かない日があるなんてことのないように!体調管理もしっかりしていきましょう笑)
ヴァイオリンレッスンに関するお問い合わせは公式ラインにて(単発レッスンは随時受付中:オンライン可)
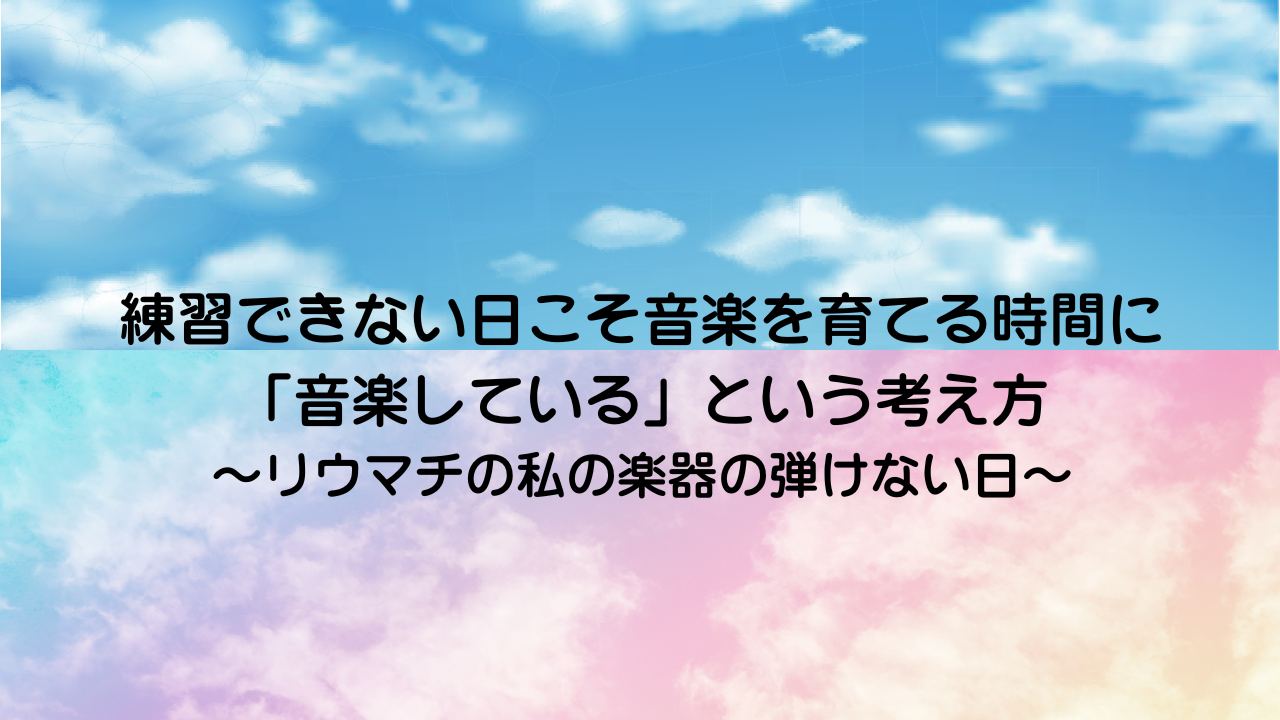
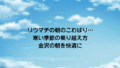
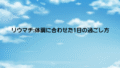
コメント