お教室の生徒さん含め、「練習してくれなくて…」という親御さんからのご相談がよくあるのでそれについてお話したいと思います。「ヴァイオリンは好きなんだけど、練習はしたくない」生徒さんからも聞かれるこんな言葉、ご家庭でこんなことしてみてください。
子どもが練習しないのは自然なこと
練習は「やらされるもの」だと続かない
残念ながら、ヴァイオリンが大好きで好きで好きでたまらなくて、練習も熱心にする子というのは少数派で、大体は練習に気持ちが向かず、後回しにしがちです。練習したいという気持ちにさせることが第一歩です。
小さな工夫で“やる気スイッチ”は入る
普段練習を見てくれているご家族の一言で、やる気のスイッチが入ったり切れたりします。その子その子の性格をよくみて、ご自身のお子さんがどの声がけでやる気が入るかもよく観察してくださいね。
声掛けで変わる!親のひと言工夫
「やりなさい」より「やってみる?」の質問形式
レッスン中でも「やりましょう!」より「やってみる?」「やってごらん?」という方が子どもたちは素直にヴァイオリンを弾き、提案することで間違えていることを直そうとしてくれることが多いです。子どもたちもすでに1人の人間としての考えがありますので、「命令より、提案」で声がけをすると練習スイッチが入るでしょう。
できたところを大袈裟に褒める!
人間には「承認欲求」というものがあり、子どもたちは特に「認められたい!」という気持ちが強いです。特に小さなうちにその欲求をしっかり満たされている子は、少しずつその欲求とサヨナラして、他を認める性格も身に付きますし、明るく朗らかな子にも育ちます。その性格育成のためにも大袈裟に褒めることはとても重要です。ただし、「できたことを褒める」です。できてないのに褒め称えることが続くと、レッスンで指摘された時にとっても大暴れしますので、「できたところを褒める」を大切にしてください。褒められることは「成功体験」の一つにもなるので、大切なことです。
環境を整えると、練習は始めやすい
楽器と楽譜はすぐ手に取れる場所におく
まずは練習しやすい環境を整えましょう。ヴァイオリンはケースにしまってあって、練習しよう!というスイッチが入ってから練習までにケースから楽器を出して、肩当てつけて、松脂塗って・・・・とやることがたくさん、それをしている間に他のことに目が入ってしまい、練習のモチベーションがなくなってしまうなんてこともあるでしょう。
私の子どもの頃の話ですが、楽器はすぐに出せるようにケースから出しっぱなし、常に肩当てもついたままで、専用の棚を母が準備して、サッと楽器を出していつでも弾ける環境でした。それが良かったのだろうなぁと思っています。
リビングなど人のいう場所で弾けるようにする
練習をリビングなど、いつも人のいるところでやるのもいいと思います。お母さんが料理をしながら見れる距離感でしょうか、日常に練習を溶け込ませることで練習が習慣となるでしょう。
習慣化は“ハードルを下げる”ことから
「5分だけ」「1回だけ」をOKにする
ヴァイオリンの初めてのレッスンの時に「毎日ヴァイオリンを触ってください」という話をします。毎日ヴァイオリンを構えるだけからスタートして「毎日触る」を習慣化します。そして「1回だけ練習する」「5分だけ練習する」と言うふうに、とにかく生活のリズムにヴァイオリンを入れるようにするんです。
時間を決めてルーティンに組み込む
習慣がついたら、ご飯を食べる、お風呂に入る・・・のように毎日の生活の「ルーティン」としてヴァイオリンが組み込まれていくと思います。
ここまでくると「練習はするもの!」としてヴァイオリンのレッスンに来ても合格がたくさんもらえたり、新しいことを学ぶ喜びが生まれたり、ヴァイオリンの楽しみ方もわかってくると思います。
ご褒美や楽しみで前向きに
練習後にシールなど
練習シール台紙を用意すると子どもたちは嬉しそうに達成させるために一生懸命練習してくれます。1回弾いたら1枚シールを貼るなどです。とあるご家庭では、この練習が終わったら、「このゲームを1回する」「1回練習をしたら、このおやつを1個食べる」などしていたと言っていました。その生徒さんもコンクールで入賞するような子に育ちました。
練習=楽しい記憶で終わらせる工夫
練習したらこうなったと言う記憶を積み重ねることで、練習が好きになってくれたら上達にも結びつきます。「楽しかった!」となる工夫をどんどんしていきましょう。
まとめ
練習しないのは子どものせいではないです。やはり、大人の助けがとっても大切です。
無理強いはせず、親も子どもも笑顔でいられることが大切です。この記事が練習に悩む皆様に届きますように。

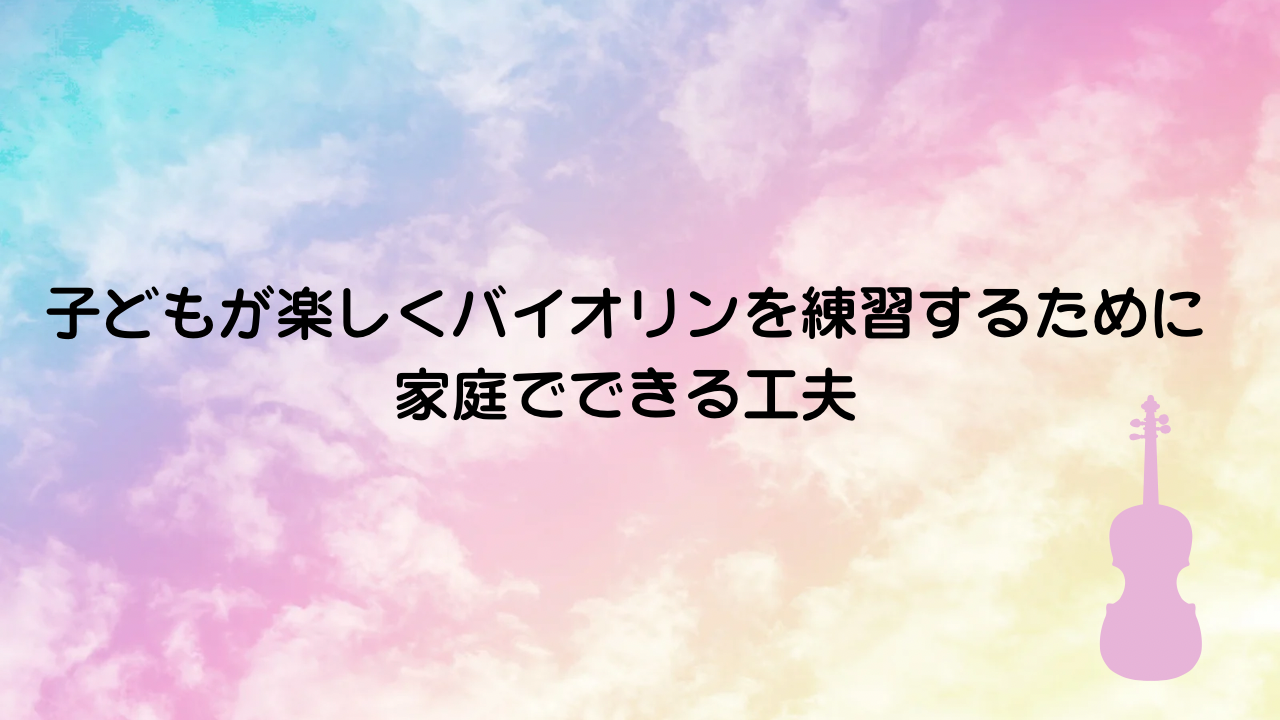
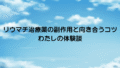

コメント